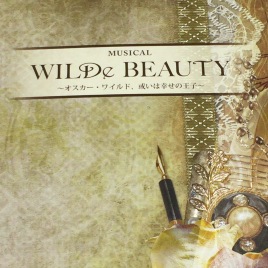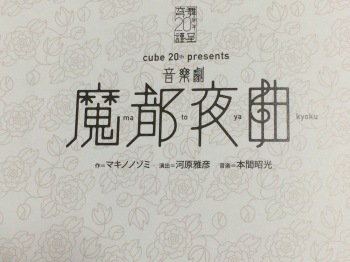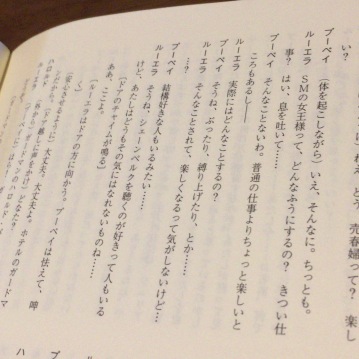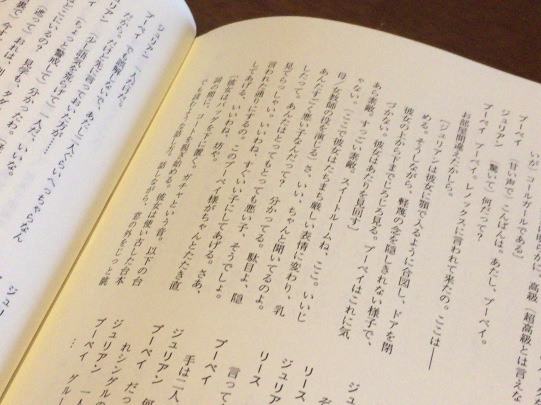終わっちゃいましたねえ。『WILDe BEAUTY』。
休演日なし、8日間ノンストップの公演だったこともあるけれど、スピード感に充ちみちた公演でした。
去年、壮さんがD☆Dの『Dramatic Musical Collection 2016』に出演したときは、2日間のゲスト出演だったから感じなかったのだけど、今回、『WILDe BEAUTY』の初日から千穐楽までを追走し、このスピード感はすごい、さすがは男所帯だわ(笑)と。
それをいちばん感じたのが千穐楽。見慣れているタカラヅカの千穐楽には、舞台全体に、ちょっと甘酸っぱい、名残を惜しむような空気が充満するものだけど、そういう感傷的なものが見事にない!
集大成を見せるべく、それぞれが集中し、役に気持ちを込めているのは共通しているのだけど、その空気感が今までなじんでいるものとはかなり違っていて、ひと言でいうとアスリート的。舞台の幕が降り、カーテンコールになったときにはもう、「やり切った!」「次、行くぜ!」と、全員が次へとウォーミングアップを始めているような感じ。男子たちの勢いと圧に押されぎみになるのも爽快で、異文化に接したときのような新鮮な感動がありました。幕のおろし方っていうのもさまざまで、こんな感じもあるんだなあと。
劇中のセリフにも出てきたけれど、「忘れていく」のも、役者にとっては必要なスキル。D☆Dの面々は、自然とその手順を踏んでいるし、女性陣の三人(壮一帆さん、小野妃香里さん、大月さゆさん)も、そこにうまく乗れていて、晴れやかだった。荻田先生とのつながりがあるメンバーばかりだったということもあるのかもしれないけど、いい座組みだったんですね。壮さんも、あいさつでは、まずD☆Dの15周年を祝福し、さゆちゃんと、かおりさんのことにも触れていました(こういうのも板に付いてきたなあと思う)。
さゆちゃんがブログで、壮さん、妃香里さん、さゆちゃんの三人を「男前女子」と書いていて、「それ!」と膝を打ったのだけど、お芝居にもそんな気質を感じました。というより、単にわたしの好みだったのか。さゆちゃんのオスカーの妹とビアズリーの姉。妃香里さんのサラ・ベルナール。どちらもとてもよかった。
さゆちゃんのブログに出てくる壮さんの笑顔がとってもいいので、記念にリンクを貼らせてください。
さゆちゃんは大好きな娘役さんで、壮さんとの共演は本当にうれしかった(『さすらいの果てに』のナース役と、『DAYTIME HASTLER』の幽霊岩の「押し合いへし合い」のダンスは忘れられません)。
カーテンコールの最後に出てきた、よっくん(東山義久さん)とえりたん(壮一帆さん)が、おそろいの衣装で手をつないだりなんかしてめちゃくちゃかわいかったことも書き留めておかなくては(笑)。
二人とも白ブラウスにジレという王子スタイル。白のブラウスの袖がちゃんと王子様っぽくふくらんでいて、愛らしいんです! 壮さんはともかく、東山さんまでもが(!)パフスリーブのお袖なんです(笑)!
荻田先生ごのみ?
と、突っ込みながら気付く。東山さんの「ワイルドの幻想」と、壮さんの「死神/天使」とがいっしょになったときに浮かび上がったものが「幸せの王子」だったのだ。
「幸せの王子」は、オスカー・ワイルドが生み出したあらゆる思考と妄想が一体となったようなもの。だから、「幸せの王子」は最後まで誰にも見えなかった。
本当に尊く美しいものは、目には見えない。
サン=テグジュペリが『星の王子さま』で書いたのと同じ。美しいものを追い求めたオスカー・ワイルドが最後にたどり着いた「天国の門」が、あの海だったのかもしれない。
考えてみれば、そんなことははじめからサブタイトルに書かれていた。「オスカー・ワイルド、或いは幸せの王子」と。そうか、だから「幸せの王子」の歌も、二人のパートがいっしょになったときに、一つの曲になったんだ。
ああ、いま、とても劇中で歌われた歌を聴きたい。
(こういうとき、宝塚歌劇のシステムって素晴らしいなと思う。少し待てば、ほぼ確実に音楽配信がされるし、映像化もされる)
来年の3月には申し込んだDVDが届くと思うので、それを楽しみに待ちましょう。
そういえば、壮さんが王子様コスをしているのを見たのって初めてだったかもしれない。「かぼちゃパンツ」でも「リボンの騎士」でもなかったけど、シックな王子様コス、とっても似合っていました。
長いとはいえない稽古期間で、こんなに濃密な舞台を作り上げるのは、さぞ大変だっただろうと思う。タカラヅカだったら1カ月半かけて作り上げていくところを、その何倍速かのスピードで進んだんだろうな…(そういうときの壮さんは、いつも以上に言葉がポンポン出てくるので、FC経由のお手紙にもそんな雰囲気が感じられて楽しかった)。
でも、こちらの世界では、それがスタンダードなのだろうとも思う。
常に早い仕上がりを求められるし、パフォーマンスにもある程度の水準と均一化が求められる。宝塚歌劇のように、初日が開いてからの変化を追っていくような楽しみ方は歓迎されないと個人的には思っているのですが、この『WILDe BEAUTY』は例外的で、ある種のストレートプレイ的な作品と同じく、役者の幅のある感情表現を楽しむことが許される「官能作品」だったと思います。
東山義久さんと咲山類さんの二人で表現したオスカー・ワイルドはもちろん、D☆Dの皆さん、そして壮さんの変化が見て取れたのは本当に楽しくスリリングだった。
ビアズレーの中塚皓平さんと、その姉のさゆちゃんとの濃密な愛の場面は、かっちりとした芝居になっている場面だったし、毎回引き込まれました。人前ではいつも仮面をつけていたというビアズレー。オスカーとの関係にも複雑なものがあるようだし、これで作品が一つできるのでは。
東山義久さんの「ワイルド」 (オスカー・ワイルドの幻想)は、次第に怪物になっていくようすがダイナミック。ラストのダンスの背中が素晴らしくて、鳥類ではない生きものについた羽の跡が見えるようだった。「瀕死の白鳥」のように静かに息絶えていくのではない、「ワイルド」な死のダンス。死を迎えるまでの、存在し続けようという壮絶なダンス。その姿が美しく、オスカー・ワイルドが求め続けた「美」とはこういうものだったかもしれないという、一つの答えを見た気がしました。
“オスカー・ワイルドの幻想”と同時に、ワイルドが愛し抜いたアルフレッド・ダグラスを演じたのも、自己愛と自虐が同居していて面白かった。
咲山類さんは「オスカー」(オスカー・ワイルドの現実)。回を重ねるごとに本当にオスカーの闇を抱え込んでいっているようで(初の大役で大変だった?)、最後のラストシーンでは、本当にげっそりとやつれて、死を前にしたオスカー・ワイルドそのものに見えました。類さんにはたおやかさや品のよさがあるので、東山さんの獣性との相性も面白く、二人で「オスカー」と「ワイルド」を分け合ったのは納得でした。
そして壮一帆さん。作品タイトルが『WILDe BEAUTY』だから、全体を「ビューティー」にまとめあげるのが壮さんの役どころだったのかな。東山さんと類さんのオスカー・ワイルドの内から出てきたものとは違う「美」のかたち。天使で死神でフローレンスでコンスタンスで。永遠に女性的なるもの?
役が入れ替わり、髪型も変わる壮さんを見ながら、何度も考えさせられました。美しさとはなんだろうって。
壮さんのフローレンスは、見た目は美しいのに、どこかおどおどしているような固いところがあって、不健康な少女のよう。幻想的なメイクは、ティム・バートンの『アリス・イン・ワンダーランド』をイメージしていると聞いたからか、『ナイトメア・ビフォー・クリスマス』のサリーのようにも思えました(もちろんほめていますよ! 大好きです!)。ツギハギの衣装も似ているし。
壮さんのもつ透明感と冷たい美しさは、さながらヨーロッパの知性派女優。束ねられた髪をふわりとほどいてフローレンスになる瞬間なんかほんとうにビューティーで、かつ自分ごのみで(笑)、初日に見たときには比喩ではなく息を飲んだし、身を乗り出して見ていたかもしれません。
こういう女性を演じる壮さんを観るのは初めてだったけれど、初めてではないのです。『〜夢と孤独の果てに〜 ルートヴィヒII世』新人公演のディルクハイム伯爵。『送られなかった手紙』。『ル パラディ』のレーヌ・ド・ニュイ。『カナリア』のプロローグ。『ベルサイユのばら』のフェルゼン。『心中・恋の大和路』。
女性としての役ではなかったけれど、そういう美質って、男性を演じても女性を演じても変わらないもの。そうだ、わたしは壮さんのこういうところが好きだったんだと、ちょっと懐かしい気持ちになりました。
個人的には、壮さんにはヨーロピアンな雰囲気があるから、タカラヅカの耽美的な世界も合うと、ずっと思っていたので、在団中はあまり縁がなかったことに、「みんな、壮さんのパブリックイメージに影響されすぎ! 」 と、けっこう怒ったりしていたのですが(笑)、タカラヅカのカッコ付きの耽美を担当するには、壮さんはすこやか過ぎたり、糖度が低かったり、自己愛が足りなかったり、地に足が付き過ぎていたりしたのかもしれないと、壮さんがこちらの世界の舞台に立つようになったいまは思います。
でも、そんなところが壮一帆さんの変わらない美質だし、そんな壮さんだったから、『タランテラ!』の囚われの男にあんなにも惹かれたのかもしれない。と、ここに来て、さらなる気付き(笑)。
それに、そういうゆらぎのない「美しさ」をもっているって、とても素敵なこと。きっと、これからの壮さんを支えてくれると信じています。
実際に『WILDe BEAUTY』でも、回を重ねるごとに、フローレンスやコンスタンスを演じるときには儚さの方へ振れて行き、“死神、或いは天使”のほうは、タカラヅカファンがイメージするわかりやすい死神ではなく、ある意味人間っぽい方へ振れ、素のソウカズホさんを感じるお茶目なところが出てきた気がします。それが、ちょっと外されたというか(笑)、面白かった。
なんだか、とりとめがなくなってきてしまいましたが、つまり『WILDe BEAUTY』は、ここでオスカー・ワイルドの生涯をそうとらえたように、本当の美しさとは何かを考える物語だったともいえるのかもしれません。
耽美という言葉についても考えました。
タカラヅカ好きな人は、耽美的なものを好み、それを上等とする傾向が強いと思うのですが、こちらの世界で同じようにやっても成立させるのは難しい。あれは、宝塚歌劇という異空間でのみ成立するものなのだ。
そして、この『WILDe BEAUTY』や荻田先生が描こうとしている世界を、「耽美的」という言葉だけで表現しようとしたら、こぼれ落ちてしまうものがたくさんある。観た人が「耽美的」と感じる世界をつくることを目的とはしていないはずだから。
…と、そんなことも思ったりしました。
『WILDe BEAUTY』パンフレットに掲載された対談でも、脚本・演出の荻田先生はこんなふうに語っています。
荻田 「……(『WILDe BEAUTY』でやろうとしているのは)アングラ的に綺麗な世界なので、壮さんのカラーがどうなるか? と思っていたのですが、やはり現実世界に戻ってみれば、意外とフェアリーなものがあるんだなと」
壮 「私が!? フェアリー?」
荻田 「そうそう、宝塚の世界においては現実的なものがあったし、今ももちろんそれもあるんだけれども、やっぱり世間一般の役者さん、女優さんの中に入るとフェアリー要素が確かにあるなと」
壮 「本当ですか?」
(略)
荻田「わからないでしょう? でも『えりたん(壮の愛称)もフェアリーなのね」と改めて思ったから、今回はそれを出してもらうチャンスなのかなと」
D☆Dについても、長く舞台を一緒にしてきているので「現実の要素がとても強い人たちなんです。この世の者としてちゃんと知っている人たち」と評し、
荻田「……お互いの、ある種デリケートじゃない部分が、作品のいびつさを照射してきてくれていて、自ずと新たな方向に船は進んでいるなと」
荻田先生の言っているのはリップサービスではなく、本当に、東山さん、そして壮さんの内から出てくるすこやかさ、揺るぎなさが、作品全体のバランスを取っていたのかもしれないなと思う。
それに、荻田先生。「あなたこそ、フェアリー」です(笑)。これだけ上品なアングラをやれちゃうのってすごい。タカラヅカのOBだからこそだと思います。
それには斉藤恒芳メロディーも大いに力を貸してくれていて、この揺れまどう旋律あっての荻田ワールドなのだなあと。
壮さんの歌う曲も、遭難しそうな難曲ばかりでしたが(笑)、歌うほどに、気持ちよさそうに歌っていて。でも、乗りこなすのは難しいけれど、美しい曲なので、また、コンサートなんかで歌ってもらえたら。それも楽しみにしていようと思います。
そして、オスカー・ワイルドの童話の朗読なんかもしていただきたいなあ。「幸せの王子」はもちろん、「若い王」とか「星の子」とか。
荻田先生、よっくんとえりたんの「夫婦漫才」がどんなものになるか、それはとっても見てみたいけど、フェアリーの壮さんのほうもよろしく。
『WILDe BEAUTY』も。いつかまた。
DIAMOND DOGS の皆さんのブログと、twitterで見た荻田先生と壮さんのツーショット。レアだから、載せちゃいます(*^▽^*)